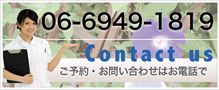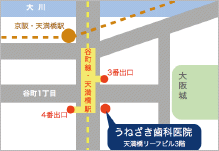歯の神経をとるということ
詰め物が外れた、歯が欠けた。 痛くないし大したことはないだろうと治療に出かけたら、歯科医師から“神経をとります”と言われることがあります。 えっ?と全ての方が思われるはずです。
実は、これは私たち歯科医師にとっても悩ましい状況です。
若年者の歯は未成熟なエナメル質が急激に崩壊して、虫歯の初期段階から痛みが発現します。 対して成人の歯は十分に石灰化して成熟しているため、エナメル質、象牙質の崩壊は非常にゆっくりと進行します。 極端な症例では、知らないうちに神経(歯髄)が侵されてしまっていることもあります。
昔の歯科医師は迷うことなく神経をとりました。 しかし、最近ではルーペやマイクロスコープで歯の中を診るようになりました。 すると、これはたまらんなと言う状況に気付きました。
歯の神経がある場所は”歯髄腔”と言います。 これが患者様ごとに個性のある複雑な形をしています。 これを治療するためには、以前お話ししたラバーダムだけでなく特殊な器材を使用します。
私が歯学生として講義を受けた40年近く前から大きな変わりはなく、今でも肉眼による治療術式が学部教育の現状です。
つまり、複雑な形態の歯髄を治療のために、マイクロスコープやラバーダムなどの助けを借りて、少しでも術後の予知を高めようとしているのが現状です。
それではどうすれば歯の神経をとることを防ぐことができるでしょうか? 基本は早期の虫歯を発見することです。 早期発見は目視とレントゲンによる診断で見つけるしかありません。
もう一つ、患者様の”違和感”も重要な診断情報です。 3ヶ月や6ヶ月の健診時には、”今は気にならないけど、こんなことがあった” と言うことをぜひお伝えください。
天満橋 谷町1丁目
うねざき歯科医院
補綴専門医 指導医